メディカルハーブセラピストの資格を取ったら、どんな働き方ができるのかは多くの受講希望者が一番気になるポイントだと思います。
ハーブの資格というと「サロンを開く人だけが使うもの」というイメージを持たれがちですが、実際にはもっと幅広い活用方法があります。
販売やカウンセリングだけでなく、講師業・オンライン発信・地域活動・本業との掛け合わせなど、ライフスタイルや性格に合わせて自由に選べるのがこの資格の強みです。
ここでは、メディカルハーブセラピストが実際にどのような形で仕事につなげているのか、代表的な6つのパターンを紹介していきます。
当サイト限定の情報も盛り込んだので、記事の手順でメディカルハーブセラピストの仕事をしましょう。
メディカルハーブセラピストとは?

資格の概要と役割
メディカルハーブセラピストは、日本統合医学協会の認定資格です。
ハーブを育てるために必要な土や水やり、日当たりなどの基本を学べます。
自分でハーブを育てられるようになると、生活にすぐ取り入れられます。
ハーブを使ったスキンケアやリラックス方法、体調管理など、日常生活で実際に使える方法を知ることができるでしょう。
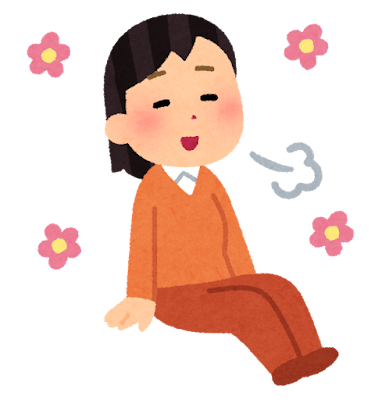
不調の改善や健康維持に役立つ、代表的なハーブ21種類について、効能や使い方を詳しく学べます。
たとえば「カモミールで安眠」「ペパーミントでリフレッシュ」など、具体的に役立つ知識です。
複数のハーブを組み合わせて、自分好みのハーブティーを作れるようになります。
香りや味わいを調整して楽しめるのも魅力です。

ハーブを作るところから組み合わせるところまで総合的に学べます。
アロマセラピストとの違い
メディカルハーブセラピストは植物そのもの(ドライハーブなど)を使って、身体の内側や外側から健康をサポートする専門家に対し、アロマセラピストは植物から抽出された香り成分(精油)を使って心身のバランスを整える専門家です。
| 項目 | メディカルハーブセラピスト | アロマセラピスト |
| 扱うもの | ハーブ(植物そのもの) | 精油(植物の芳香成分) |
| 使用方法 | 飲む・漬ける・湿布など | 嗅ぐ・塗る・香らせる |
| 主な目的 | 体質改善・予防・健康維持 | リラックス・美容・メンタルケア |
| 身体への取り入れ方 | 内服O.Kのものがある | 原則、飲用不可 |
| 活かし方 | 料理・ティー・薬草療法 | マッサージ・香り・空間演出 |
実は両者は相性が良く、サロン・教室・介護・カウンセリングなどで併用されるケースも多いです。
「内側ケア(ハーブ)+外側ケア(アロマ)」の組み合わせは、ナチュラルケアの現場では定番になります。

メディカルハーブセラピストは植物に興味がある人に向いている資格です。
メディカルハーブセラピストの仕事とは

活躍できる職場・フィールド
- 医療・福祉分野
- 教育・講師活動
- リラクゼーション・美容分野
- 商品開発・販売
- 農業・栽培分野
- 企業・法人とのコラボレーション
があります。
実際の仕事内容
クリニックや病院の補完療法として、医師の指導のもとで、患者さんにリラックスや体調改善をサポートするハーブティーの提案などができます。
介護施設・福祉施設で高齢者に優しいハーブティーやハーブを使ったセルフケアを紹介することで、日常の健康維持や癒しを提供することが可能です。
カルチャースクール・市民講座でハーブの基礎知識や活用法を一般の方に伝える講師として活動できます。

資格取得スクールや専門学校でアロマやハーブの専門講座で講師を担当し、セラピストを目指す人の育成に関われます。
オンライン講座・ブログ・SNSで情報発信を通じて、広く一般の方に知識を伝えながら、自分のブランドを築くことも可能です。
エステサロン・リラクゼーションサロンで、トリートメントと組み合わせて、ハーブティーの提供やカウンセリングを行えます。
スパ・ホテル・リゾートで、滞在客向けにウェルネス体験としてハーブを取り入れたサービスを展開が可能です。

美容室の待ち時間にハーブティーを提供したり、リラクゼーションメニューの一部にハーブケアを組み込めます。
自分のブランドでブレンドハーブティーやハーブソルト、ハーブバス商品を開発できます。
自然派ショップ・雑貨店での勤務で、ハーブ製品の知識を活かして販売やアドバイスが可能です。
通販ビジネスで、ネットショップを開設し、オリジナルブレンドや教材を販売する形で独立も可能です。

ハーブ農園・体験型観光施設でハーブの栽培から販売、ワークショップまでを行い、観光客に楽しんでもらえます。
自家栽培したハーブを使って、ティーやクラフト製品を作り販売します。
ハーブを地域資源として活用し、農業や観光の活性化に貢献することも可能です。
食品メーカーや飲料メーカーでハーブを使った新商品の企画に携われます。

化粧品・健康食品業界で、機能性やリラックス効果を活かした製品開発の監修やアドバイザーとして関われます。
企業向け健康セミナーで、社員の健康維持やメンタルケアを目的とした研修や講演を行う事が可能です。
仕事で人に価値を提供できます。
在宅ワークや副業としての可能性
メディカルハーブセラピストという仕事は、自分の心や体を癒しながら、人にもリラックスや健康のサポートを届けられるのが魅力です。

つまり、自分のためにも、人のためにもなる仕事です。
さらに、専門的な知識を活かして
- ハーブの講座を開く
- ブレンドティーを販売する
- ハーブを使った商品の企画を行う
といった形で、副収入を得ることもできるでしょう。
こうした理由から、メディカルハーブセラピストは、「癒し」「人の役に立つ」「収入にもつながる」という3つの魅力を持つ、注目の副業として人気が高まっています。
副業をするなら、小さく始めることをおすすめします。
メディカルハーブセラピストに向いている人

必要なスキル・知識
メディカルハーブセラピストとして活躍するためには、単にハーブの名前や効果を知っているだけではなく、人の体や心の状態に合わせて安全かつ効果的に使いこなすスキルが必要です。

メディカルハーブセラピストの土台となるのが、「ハーブそのもの」に関する知識です。
- 各ハーブの有効成分(成分化学)
- 効能・作用(鎮静・消化促進・抗炎症など)
- 使用部位(葉・花・根など)とその抽出方法
- 適切な保存方法やブレンドの相性
たとえば、カモミールにはリラックス作用のあるアピゲニンが含まれ、ペパーミントは胃の不快感を和らげるメントールを多く含みます。
こうした科学的な理解が重要です。
「メディカル」とつくように、身体の仕組みや不調のメカニズムを理解することも欠かせないです。
- 人体の構造(消化器・呼吸器・神経・内分泌など)
- 体の不調がどのように現れるか(ストレス・ホルモン・免疫など)
- 薬や病気との相互作用・禁忌事項
これにより、体調や体質に合わないアドバイスを避け、安全で効果的なハーブ提案ができるようになります。
メディカルハーブは、単品で使うよりもブレンドによって効果を高めることができます。
- 目的別ブレンド(リラックス・免疫サポート・冷え改善など)
- 香りや味のバランス調整
- ハーブティー・軟膏などへの応用方法
感性と理論の両方を活かして、オリジナルブレンドを提案できることがプロのセラピストの強みです。
クライアント一人ひとりの悩みや体質を丁寧に聞き取り、最適なハーブを提案するためには、傾聴力・共感力が重要です。
- 相手の生活習慣やストレス要因を理解する
- 体調や気分に合わせて無理なく続けられる提案をする
- 精神的な安心感を与える会話力
「ただのアドバイス」ではなく、「寄り添いながら一緒に整える」姿勢が信頼を生みます。
理論だけでなく、実際にハーブを日常生活に取り入れるスキルも大切です。
- ハーブティー・ハーブバス・ハーバルオイルなどの作り方
- 精油(アロマ)との組み合わせ
- 季節や年齢に合わせた提案方法
この実践力があると、サロンや講座でも「すぐに使える知識」として信頼されます。
最近では、SNSやブログなどで「ハーブのある暮らし」を発信するセラピストも増えています。
- わかりやすく伝える文章力・プレゼン力
- 講座やワークショップでの指導力
- 写真・デザイン・オンライン講座運営のスキル
学びを「伝える力」に変えることで、個人でも活動の幅が大きく広がるでしょう。
メディカルハーブセラピストの資格を取得し、実践するとこれらのスキルや知識が身に付きます。
向いている人の特徴
看護師・介護士・保育士・カウンセラー系によくいるタイプで、「大丈夫?」「疲れてない?」と自然に声をかけられる性格やストレスケア・不眠・更年期など、特に心の不調や慢性不調に寄り添いたい人に向いています。
「植物を育てるのが好き」「森に行くと落ち着く」タイプで名前を覚えるのが得意・観察力があり、ハーブを香りだけでなく生活道具として活かす楽しみがある人です。

自分よりも相手に話させる方が得意で「この人になら話してもいい」と思われる安心感を持ち、共感しながら提案する力を持っている人です。
「ノートまとめが好き」「辞典を見るのが好き」タイプで成分・効能など理論が入ってくるとワクワクする人は講師・講座開催・コンテンツ発信に強いでしょう。
スキンケア・スイーツ・お茶・アロマなどが好きで「見た目の癒し」「味の癒し」など感覚を大事にするタイプの人は商品企画やレシピ開発、イベント向きです。
「薬やサプリより自然なもので整えたい」「子どもの不調に優しく対処したい」「更年期・PMS・ストレス解消など自分のために武器を持ちたい」人も向いています。

この中の一つでも当てはまれば、メディカルハーブセラピストに向いていると言えます。
まずは、自分がどのタイプか確認をすることです。
メディカルハーブセラピストの収入とキャリアパス

平均的な収入の目安
メディカルハーブセラピストは、ハーブの知識・カウンセリング能力・提案スキルが求められ、かつ「物販」「講座」「オンライン対応」など複数の収益源を持ちやすい立ち位置です。
そのため、セラピスト全体の平均より若干幅が出やすいです。
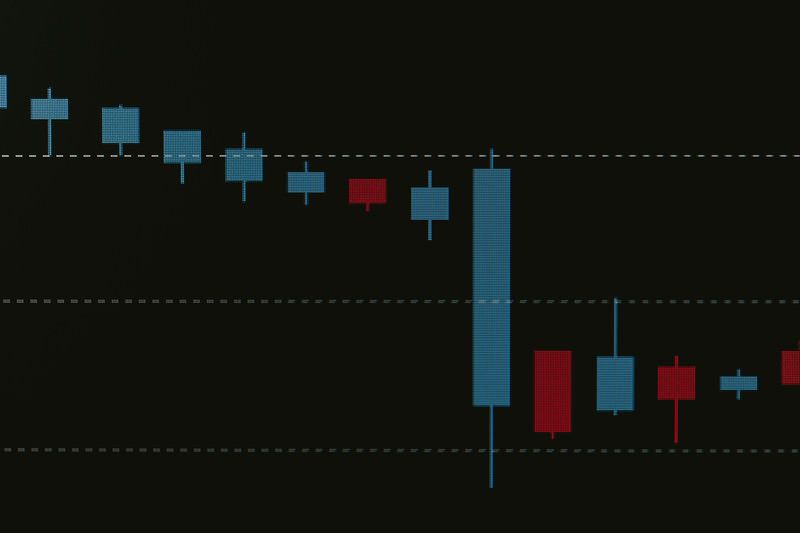
目安として使えるレンジを、働き方別に整理します。
| 働き方 | 年収の目安レンジ | 解説 |
| パート・アルバイト中心 | 約 100〜200 万円 程度 | 勤務時間が限定的、固定収入が小さいケース |
| 固定給+歩合を併用 | 約 200〜300 万円 程度 | サロン勤務+ハーブ提案や物販を少し行う |
| 専業・自営型 | 約 300〜500 万円 程度 | 個人顧客・講座・物販を組み合わせる運営ができればこのレンジが現実的 |
| 成功・拡大型 | 500 万円超も可能 | ブランド力・集客力がついたり、拠点を複数持つようになるとこのあたりも狙える |
特に「専業で自分のハーブ教室・物販・オンライン講座を複合的に行う人」は、350〜450 万円前後になるケースも多いと予測されます。
メディカルハーブセラピストだけで大きく稼ぐのは難しいです。
独立・開業の流れ
メディカルハーブセラピストとして独立を目指す場合、最初の一歩は「資格を取ること」ではなく、「どんな形で人にハーブを届けたいのか」を決めることから始まります。
ハーブティーの販売をしたいのか、個人向けのカウンセリングやセッションを提供したいのか、あるいは講座やワークショップを開催したいのかです。

この方向性によって、その後の準備の内容が変わってきます。
方向性が固まったら、まずは基礎知識を固めるために資格講座を受講しましょう。
通信講座で学びながら、自宅でブレンドの練習をしたり、SNSで学習記録を発信したりしておくと、開業後のファンづくりにもつながります。
資格取得後すぐに店舗を構える人は少なく、多くの場合は「副業的な活動」からスタートします。

たとえば、自宅やカフェを借りて少人数のワークショップを月に数回開いてみたり、BASEやminneなどのネットショップでオリジナルブレンドを販売してみたりすることです。
ここで大切なのは「いきなり大規模にやらない」ことです。
小さく始めて、お客様の反応を見ながら内容を調整していくことで、無理なく形にしていけます。
活動が軌道に乗ってきたら、屋号を決めて開業届を税務署に提出し、正式に個人事業主として登録します。

あわせて仕入れ先の確保やパッケージデザイン、ホームページ・SNSの整備などを進めていきましょう。
講師業中心でやる場合は、オンライン講座用の資料づくりや動画撮影の環境を整えます。
ここまで来たら「開業」と名乗れる状態になりますが、実際の仕事はそこから先が本番です。
リピーターを増やすには、商品やサービスの質だけでなく、「この人から買いたい・学びたい」と思ってもらえるストーリーや人柄の見せ方も重要になります。

セラピストとして独立するというのは「自分自身がブランドになる」ということでもあるため、自分のライフスタイルや考え方を丁寧に発信していくことが、集客と信頼の大きな柱になります。
仕入が絡んでくるので、簿記の知識があると自分の事業の儲けが把握できるでしょう。
他資格との組み合わせで広がる仕事
メディカルハーブセラピストは、単独でも健康やリラクゼーションの分野で活躍できますが、他の資格と組み合わせることで仕事の幅は一気に広がります。
例えばアロマセラピストとしての知識があれば、香りとハーブティーを組み合わせた心身ケアを提案できるようになりますし心理カウンセリング系の資格を持っていればストレスケアやメンタルサポートのセッションに、ハーブを自然療法的なサポート手段として取り入れることができます。

またヨガやピラティスのインストラクターがハーブの知識を身につければ、レッスン後に体調に合わせたブレンドを提供する「内側から整えるレッスン」として差別化ができるでしょう。
管理栄養士・食育系の資格と組み合わせれば、食事指導の一環としてハーブを「調味料」ではなく「機能性のある食材」として提案することが可能になります。
さらに看護師や薬剤師のような医療系の資格を持つ人であれば、セルフケア講座や地域イベントなどで「医療の知識に裏付けされた自然療法のアドバイス」ができるため、説得力のある講師・相談員として信頼を得やすくなります。
このように、メディカルハーブの資格はそれ単体で職業を決定づけるというよりも、「今持っている専門性に温かみと柔らかさを加える装飾品」のような役割を果たしてくれるものです。

だからこそ、自分がすでに持っているスキルや経験とどう掛け合わせるかを考えることで、働き方は無限に広がっていきます。
他資格とメディカルハーブセラピストを掛け合わせることで、独自性を生み出せます。
メディカルハーブセラピストの学び方と資格取得方法

通信講座と通学講座の比較
| 比較項目 | 通信講座 | 通学講座 |
| 学習スタイル | 自宅で自分のペースで学ぶ | 決まった日時に教室で学ぶ |
| 時間の自由度 | 高い(スキマ学習可) | 低め(固定スケジュール) |
| 受講費用 | 比較的安い/交通費不要 | やや高め/交通費や実習費が発生 |
| 実技・実習 | 動画・教材キット中心 | 対面で直接指導を受けられる |
| 質問・サポート | メールや添削などのサポート | その場で即質問できる |
| 資格取得スピード | 自分次第で早くも遅くもなる | カリキュラムに沿って一定ペース |
| 人脈・交流機会 | 基本的には少ない | 講師や受講生と繋がれる |
| 向いているタイプ | 忙しい人・一人で集中したい人 | 直接習いたい人・仲間と学びたい人 |
受験資格・試験内容
日本統合医学協会が認定するメディカルハーブセラピスト資格は医学的な専門知識を前提としたものではなく、ハーブを生活やセラピーに取り入れたい人のために作られた、実践型の民間資格です。
受験資格に年齢や学歴の制限はなく、協会が提供するオンライン講座を修了すれば、誰でも試験を受けて資格を取得できます。
日本統合医学協会の講座はより現場目線の内容になっていて、ハーブの効能を覚えるだけでなく、実際にお客様にどう提案するかどのようにカウンセリングを組み立てるかといった使い方に重点が置かれています。
試験も堅苦しい会場試験ではなく、講座修了後のオンライン試験で行われるため、在宅で自分のペースで合格を目指すことができるでしょう。

学習の難易度としては「しっかり取り組めば必ず取れる資格」という位置づけです。
この資格は、医療現場での肩書として使うよりも、個人サロンや自宅教室、オンラインでのワークショップなどで「自然療法のアドバイザー」として活動したい人に向いています。
特に、すでにアロマや心理カウンセリング、ヨガなどの資格を持っている人がハーブの知識を加えることでセラピーの幅が広がったり、メニューに内側からのケアという提案ができるようになります。
もちろん、何も資格を持っていない人でも、ここから自然療法の世界に入る第一歩として選びやすいのがこの協会の特徴です。

受験資格はなく、計画的に学習をすれば無理なく続けられます。
学習の流れと勉強法
日本統合医学協会のメディカルハーブセラピストを目指す場合、まずはオンライン講座を申し込むところから学習がスタートします。
教材としてはテキストに加え、動画講義がセットになっていて、最初のうちは植物の基礎知識や身体の仕組みといった座学中心の学習が続きます。
ここで重要なのは単語を丸暗記するのではなく、「このハーブはどんな香りで、どんな味がして、体のどの働きに役立つのか」というように、五感とセットで理解していくことです。
動画を見ながら同じハーブティーを淹れて味わってみたり、香りを嗅ぎながらテキストを読み直すことで、知識がぐっと記憶に残りやすくなります。

学習が中盤に差し掛かると、ブレンドの考え方やカウンセリングの実践方法といった、より実務に近い内容へ進みます。
この段階では「自分が誰のどんな悩みにハーブを提案するとしたら?」と具体的な人物像を思い浮かべながらケーススタディを繰り返すと応用力が身につくでしょう。
もし身近な家族や友人がいれば、ちょっとした不調や気分に合わせたハーブティーを淹れてあげて反応を聞くのも立派な実習になります。
試験対策としては、公式テキストの確認テストを繰り返すのが基本になるが、暗記が苦手な人は「声に出して説明できるかどうか」を基準に復習するとよいです。
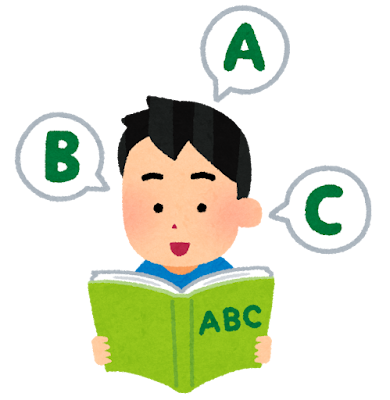
たとえば「ペパーミントの作用は?」と自分に質問して声に出して答える練習をすることで、試験だけでなく将来お客様に説明するときにも役立つ話せる知識として定着します。
全課題を終えたら、あとは試験を申し込み、オンラインで受験する形になります。
合格後は1ヶ月程度で資格認定証書が郵送されるため、SNSや名刺、ブログなどに掲載して活動準備を進めるとよいです。
特に独立を視野に入れているのであれば、学習中から日々の気づきや試したブレンドを記録しておくと、将来そのままSNS発信やワークショップのネタとして活かせます。

講座はオンラインなので、マイペースに学習を進めたい人におすすめです。
メディカルハーブセラピストの仕事を始めるために
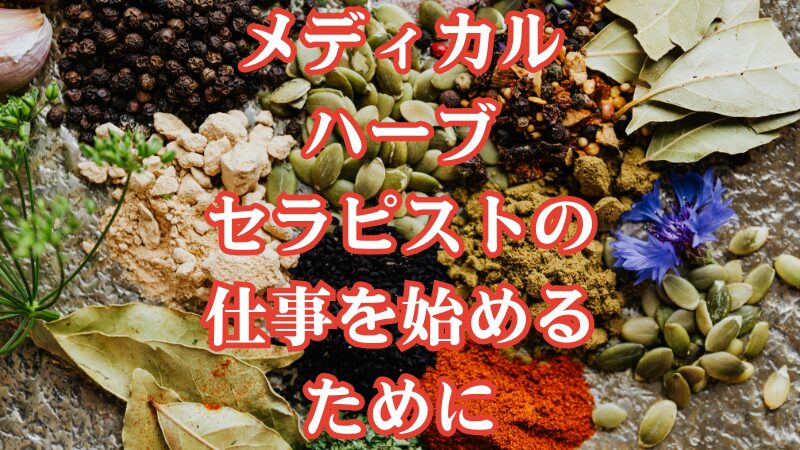
将来性と今後の需要
メディカルハーブセラピストの将来性は、近年の健康志向の高まりとともに着実に広がっていくでしょう。
特に「薬に頼りすぎず自然の力で体を整えたい」というニーズが年齢や性別を問わず増えており、ドラッグストアでのハーブティー売り場の拡大や、オーガニックカフェ・漢方サロン・ウェルネス施設の増加などにもそれが現れています。
医療や介護の現場でも、心身のケアにハーブやアロマといった自然療法を取り入れる動きが広がっており、専門的な知識を持つ人材への期待は高まっています。
今後の需要として大きいのは、「予防医療」「メンタルケア」「フェムテック(女性の健康領域)」といった分野です。

特に更年期やPMSなど、病院に行くほどではないが悩みが続く人に向けたセルフケアの提案はハーブの得意領域であり、相談役として寄り添えるセラピストの存在は貴重になっていきます。
また、リモートワークの普及によるストレス・不眠・自律神経の乱れといった現代的な不調に対しても、即効性より「心地よさ」を重視するハーブの提案は受け入れられやすいです。
さらに、資格を活かした働き方が一つに限定されない点も将来性の後押しとなっています。
自宅サロンやオンライン相談、物販やレシピ販売、カフェやヨガ教室とのコラボなど小規模からでも始めやすく個人の得意分野に合わせて活動の幅を自由に広げられます。

AIや機械化が進む中で、人と人が会話しながら体調や気持ちに寄り添う仕事はむしろ希少価値が増していく領域であり、「癒やし」「信頼」「安心感」といった感情に関わる職業は今後も長く必要とされるでしょう。
つまりメディカルハーブセラピストは、大きな市場で一気に拡大する職種というよりも静かに、しかし確実に求められる存在として時代の流れに寄り添いながら長く続けられるライフワーク型の仕事であるといえます。
人々に求められ、徐々に大きくなっていく市場になりそうです。
メディカルハーブセラピストの仕事をするためのQ&A(よくある質問)
メディカルハーブセラピストの難易度は?
メディカルハーブセラピストの資格の難易度は、テキストを見ながら受験できるため比較的低めと考えられます。
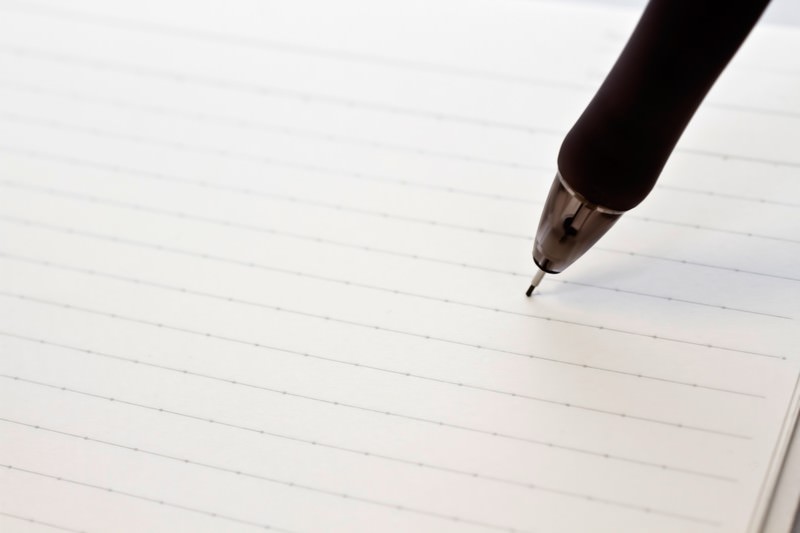
合格率は約80%、合格基準は70~80%以上の正答率が目安とされており、ハーブの知識を体系的に学ぶための登竜門として位置付けられています。
まとめ:メディカルハーブセラピストの仕事は暮らしに寄り添うサポーター
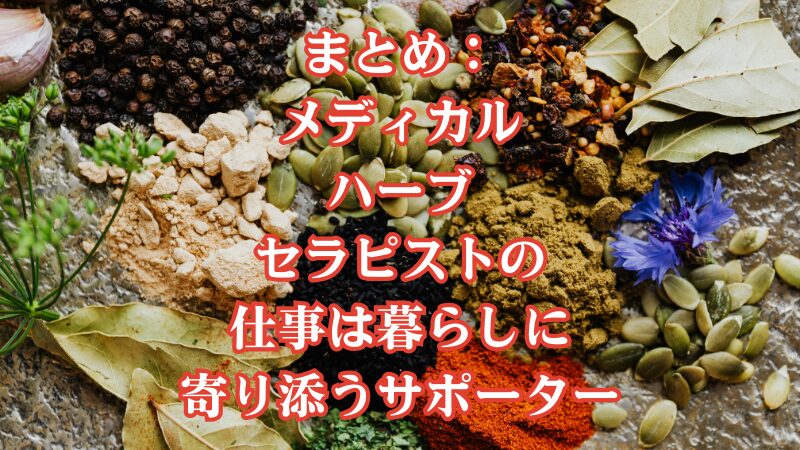
メディカルハーブセラピストの仕事は、単にハーブの知識を伝えることではないです。
病気でもない、だけど元気とも言い切れない「グレーな不調」を抱えている人のそばに立ち、そっと背中を支える存在です。
たとえば、眠れない夜に寄り添うのはカモミールティーになります。

何もできない日でも、ハーブを一杯淹れるだけで「今日はそれができた」と思わせてくれる小さな達成感があります。
メディカルハーブセラピストは、そんな植物の力と言葉を組み合わせて、誰かの「今日」をそっと支えてくれるでしょう。
医者のように診断を下すわけでもなくカウンセラーのように深い対話に踏み込むわけでもなくもっと日常的で、もっと自然体な距離感で、その人の暮らしに寄り添います。
それは「治療」ではなく「伴走」に近い役割です。

誰かが悩みを打ち明けたとき、「そんなときはこのハーブが助けになるかもしれません」と提案できます。
家族が疲れて帰ってきたときに、「今日はローズマリーにしてみたよ」と一杯の香りを差し出します。
そうした小さな行為の積み重ねが、人間関係を温め、生活を深く満たしていくでしょう。
メディカルハーブセラピストは「商品を売る人」ではなく癒やしを手渡す人です。

たとえ言葉や理屈が届かなくても、ハーブの香りなら届くことがあります。
だからこそこの仕事には、資格以上に「人の気持ちに寄り添う優しさ」や「相手のペースを尊重する余白」が求められます。
派手さはないが、確かに誰かを支えてます。
その実感こそが、この仕事の一番のやりがいです。
人にハーブを届けるために、この記事の内容を順番に進めてくださいね。


